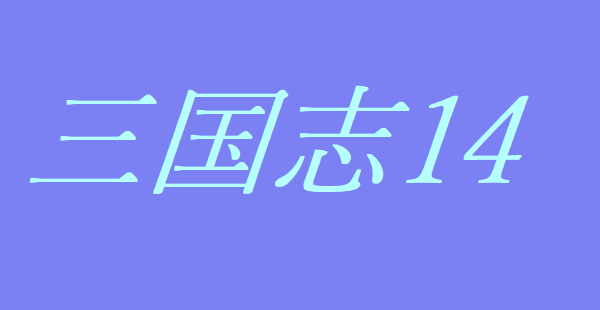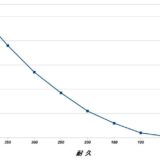部隊能力、戦法のダメージ計算式と検証してきたので、
今回は部隊戦のダメージ計算式です
1部隊 VS 1部隊の戦闘を想定しています
複数部隊、すなわち包囲効果の影響はそのうち…
実際のところ計算式は複雑なので、
完全に把握する必要はありませんが
仕組みを知っておくと
戦闘前に結果が予測できて便利かもしれません
なお、検証は難易度上級で行いました
部隊戦のダメージ計算式
以下の式でダメージを近似できます
部隊能力1500くらいまでしか試していないので
それを超えると誤差が大きくなると思われます
部隊戦のダメージ計算式
ダメージ = (1 + 0.0000107 × 兵数) × (100 + 0.1×攻防差)^2 /100
兵数 :自軍と敵軍の兵数の合計
攻防差:自軍の攻軍と敵軍の防御の差
^2 :2乗
詳細に入る前に簡単に説明すると…
(1+0.0000107×兵数)
この部分は兵数(戦闘の規模)が多くなると
ダメージも大きくなることを表しています
(100+0.1×攻防差)^2/100
最初の「100」が基本ダメージになります
ここに攻軍と防御の「差」で補正をかけていく形となっています
では、詳細をみていきます
攻防差によるダメージへの影響
14の戦闘において押さえておきたい箇所です
ダメージは攻軍と防御の「比」ではなく、
攻軍と防御の「差」で決定している
先の数式では
(100 + 0.1×攻防差)^2 /100
にあたる部分です
実際にゲーム内で攻防差を変化させ、
ダメージの変化を測定すると
以下のようになりました (合計兵数1000のとき)
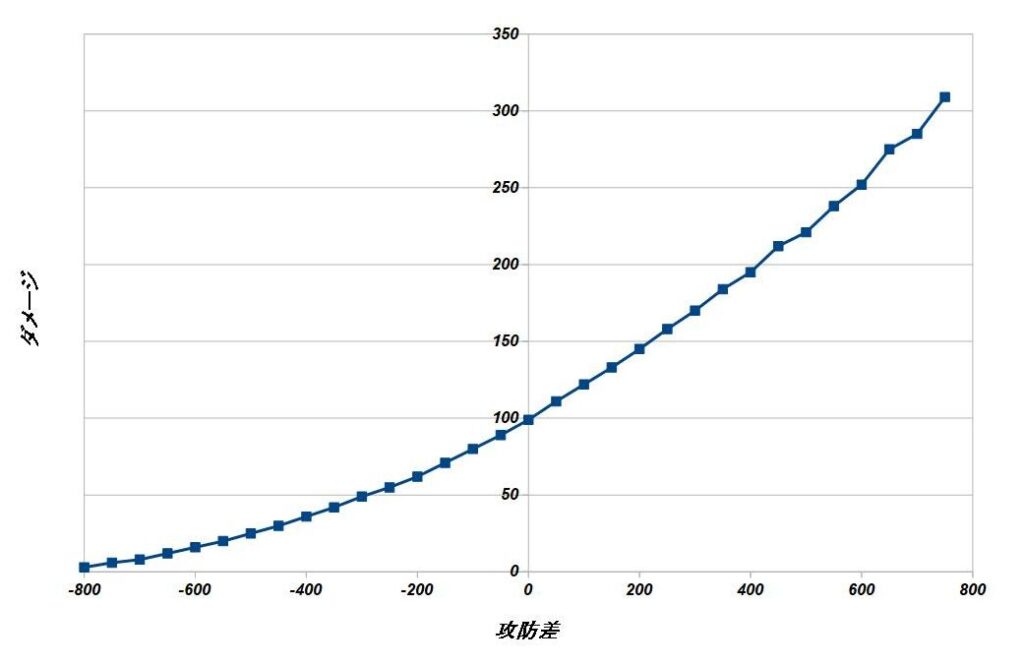
| 攻防差 | ダメージ |
| -800 | 3 |
| -750 | 6 |
| -700 | 8 |
| -650 | 12 |
| -600 | 16 |
| -550 | 20 |
| -500 | 25 |
| -450 | 30 |
| -400 | 36 |
| -350 | 42 |
| -300 | 49 |
| -250 | 55 |
| -200 | 62 |
| -150 | 71 |
| -100 | 80 |
| -50 | 89 |
| 0 | 99 |
| 50 | 111 |
| 100 | 122 |
| 150 | 133 |
| 200 | 145 |
| 250 | 158 |
| 300 | 170 |
| 350 | 184 |
| 400 | 195 |
| 450 | 212 |
| 500 | 221 |
| 550 | 238 |
| 600 | 252 |
| 650 | 275 |
| 700 | 285 |
| 750 | 309 |
ここで一番重要なのは
攻防「差」が等しければ、
どれだけ部隊能力が上がっても
同じダメージとなる
※合計兵数が等しい場合
という法則です
(ダメージの揺らぎによる誤差は生じます)
例を挙げると
ケース1
自軍:攻軍防御1500
敵軍:攻軍防御1200
ケース2
自軍:攻軍防御 600
敵軍:攻軍防御 300
この時、攻防差は等しいので同ダメージとなります
これは実際のプレイにおいて
押さえておきたい点で
特に事前に勝敗の予測をする際に役に立ちます
部隊能力を「差」ではなく「比」で見てしまうと
前者の場合、そこまで極端な差にはならない
なんて判断をしてしまうかもしれません
実際は両者ともキルレシオ1:3.5程度の
かなり厳しい戦いになります
さて、その他の特徴としては …
攻軍>防御の状況になるにつれて
ダメージが加速しやすくなり、
逆に防御>攻軍の形になるにつれて
ダメージの減り幅は穏やかになっていきます
それでもゲーム中ではダメージ1連発の状況は頻発しやすいですが…
また、グラフを見ると攻防差が+400以降でいびつな形になっています
これはダメージに揺らぎ(ランダム値?)があることを示しています
実際にプレイすると
同じ攻軍防御に揃えても状況によって
ダメージが多少異なることがあります
兵数(戦闘の規模)のダメージへの影響
さて、先の部隊攻防差に比べると
こちらはおまけ程度の補正になっています
最初に簡単に触れた通り
合計兵数(戦闘の規模)が大きくなるほど
ダメージが大きくなっていきます
ダメージが大きくなるだけで
兵数が少ない方が不利になる…という訳では無いです
ダメージ算出に関わるのは「合計」兵数で
例えば
ケース1
部隊1 5000人
部隊2 5000人
ケース2
部隊1 500人
部隊2 9500人
どちらのケースでも攻防差が等しければ
同じダメージとなります
実際にゲーム内で合計兵数によるダメージへの影響を測定すると、
以下のようになりました (攻防差0の時)
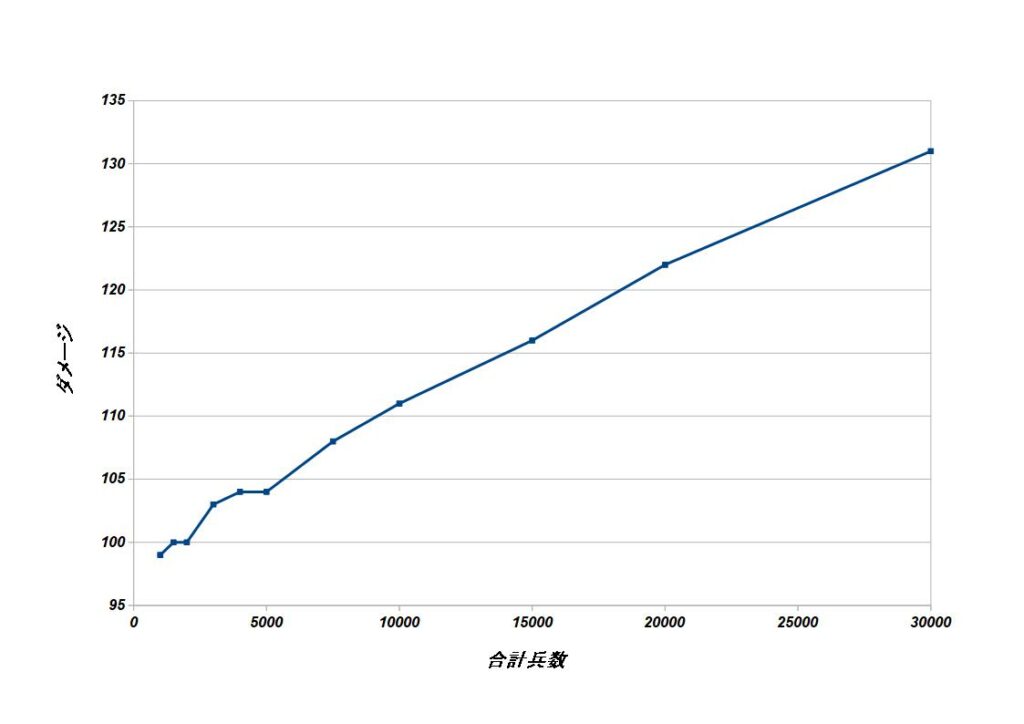
| 合計兵数 | ダメージ | 倍率 |
| 200 | 96 | 1.00 |
| 1000 | 99 | 1.00 |
| 1500 | 100 | 1.01 |
| 2000 | 100 | 1.01 |
| 3000 | 103 | 1.04 |
| 4000 | 104 | 1.05 |
| 5000 | 104 | 1.05 |
| 7500 | 108 | 1.09 |
| 10000 | 111 | 1.12 |
| 15000 | 116 | 1.17 |
| 20000 | 122 | 1.23 |
| 30000 | 131 | 1.32 |
※
表の倍率は、ほぼ補正の掛かっていない
合計兵数200の時を1.0倍としています
先ほどの攻防差のグラフと同様に
ダメージの揺らぎが発生していますが
概ね直線的な関係…
すなわち、
兵数が多くなるほど
ダメージが大きくなるという関係になります
さて、この結果をダメージ計算式に落とし込むと
1+0.0000107×兵数
という式になります
合計兵数が1000人増えるごとに
ダメージ倍率が1.07%ずつ増加する
って形ですね
合計兵数30000人で200人時の1.32倍程度、
補正は両軍にかかって不利になることは無いので
実際のプレイではあまり気にしなくても問題ないです
なお、これは実験から導き出した式なので
厳密には異なるところはあると思います
付録1:攻防差によるキルレシオの変化
せっかくなので、
部隊攻防差に応じたキルレシオの表を作ってみました
※キルレシオ:こちらが1人やられる際に何人倒せるか
ただし、魚鱗以外の陣形では
攻軍と防御が等しくないので、
ここでは魚鱗陣形のみを扱います
(厳密には魚鱗でも防御が1だけ上)
例
攻防差150なら
部隊1:攻軍防御500
部隊2:攻軍防御650
といった形です
仮に攻軍防御が
部隊1:500→1000
部隊2:650→1150
という形になっても、
キルレシオはほぼ同じになります
| 攻防差 | キルレシオ |
| 50 | 1:1.2 |
| 100 | 1:1.5 |
| 150 | 1:1.9 |
| 200 | 1:2.3 |
| 250 | 1:2.9 |
| 300 | 1:3.5 |
| 350 | 1:4.4 |
| 400 | 1:5.4 |
| 450 | 1:7.1 |
| 500 | 1:8.8 |
| 550 | 1:11.9 |
| 600 | 1:15.8 |
| 650 | 1:22.9 |
| 700 | 1:35.6 |
| 750 | 1:51.5 |
前述の通り、ダメージには揺らぎがありますので
再現しようとすると多少結果が変わります
付録2:部隊戦闘のバランスについて所感
最後に三国志14のダメージ計算式について
思うところを…
三国志14の戦闘は圧勝や惨敗など
極端な結果になりやすく、
個人的にはちょっと残念な要素です
これは、
慣れたプレイヤーが親愛やバフなどを盛り込む、
高難易度CPU勢力の地域隣接効果が非常に高いため、
部隊能力が高くなりやすく
一方で、ダメージ計算式では
攻防差200程度という比較的小さい部隊能力差でも
充分なダメージ差になるという
バランスになっているのが原因だと思います
小さい部隊能力差を想定して、
ダメージ計算式が作られているのに
想定を超えて部隊能力が高くなりすぎたため、
大味な戦闘になってしまった…
一番弊害を受けているのが
超級以降のCPU勢力同士の戦い
地域隣接効果を受けやすい防御側と
基本的にあまり受けられない攻城側で
部隊能力が違いすぎてしまうため、
一方的になってしまうことが多い
超級以降の難易度では
ダメージ計算式の方が対応しきれなかった感があります
超級以降の難易度は後出しなので
仕方がない面はありますが少し残念です
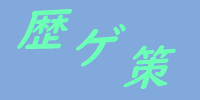 歴史ゲームの戦国策、ときどき他ゲー
歴史ゲームの戦国策、ときどき他ゲー