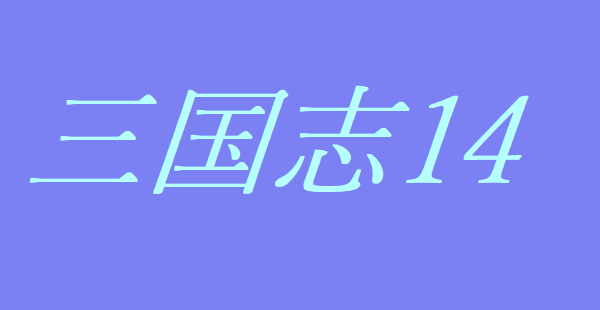久々の内政編、今回は募兵に関してです
今まで募兵に関しては、
金が溜まったらとりあえず募兵しておく
…と、割と適当にやっていました
が、調査を進めると
やり方によって、効率にかなり差がつく
コマンドだと思いました
募兵のポイント
兵士収入の近似式(募兵)
兵士収入=基礎収入 × 政策倍率 × (召募 + 教化) × 拠点種類
基礎収入= 73 × 武力倍率 × 兵舎倍率 + 人口補正 + 治安補正
・募兵の費用は地域数×金150
・都市間の格差が少ない
・収入格差は大きくなりやすい
・開発で「兵舎Lv」を上げることの効果が大きい
・召募の有無は大きい
・募兵担当は月の下旬に都市にいればOK
ということで1つずつ紹介していきます
兵士収入の近似式 (募兵)
兵士収入=基礎収入 × 政策倍率 × (召募 + 教化) × 拠点種類
基礎収入= 73 × 武力倍率 × 兵舎倍率 + 人口補正 + 治安補正
武力倍率:1+武力×0.0098
兵舎倍率:1+(兵舎Lv-1)×0.275
人口補正
| 人口 | 補正値 |
| 5500 | 1 |
| 10000 | 5 |
| 15000 | 8 |
| 20000 | 11 |
| 25000 | 13 |
| 30000 | 16 |
| 35000 | 18 |
| 40000 | 20 |
| 45000 | 21 |
| 50000 | 23 |
治安補正
| 治安 | 補正値 |
| 100 | +5 |
| 90 | +4 |
| 80 | +3 |
| 70 | +2 |
| 60 | +1 |
| 50以下 | 0 |
政策倍率
戸籍整備のLvに応じて、以下の倍率を代入
| 政策Lv | 倍率 |
| 10 | 1.40 |
| 9 | 1.35 |
| 8 | 1.32 |
| 7 | 1.28 |
| 6 | 1.24 |
| 5 | 1.20 |
| 4 | 1.17 |
| 3 | 1.15 |
| 2 | 1.13 |
| 1 | 1.10 |
| 0 | 1.00 |
召募
召募なし:1.0
召募あり:1.3
教化
教化なし:0
教化あり:0.3
拠点種類
都市:1.30
府 :1.00 (特殊地域は1.30)
港関:0.70
なお、補正の掛からない難易度上級での値である
誤差について
今回、精度はちょっと甘いです
収入が800とかを超えると、誤差±12とかあります
拠点種類(都市・港関)での誤差が多いですね…
ただ、肝心の兵舎Lvと武力に関しては
そこそこの精度になっているんじゃないかと
募兵の仕様
さて、近似式の紹介も終えたので実践編
まずは募兵の仕様です
募兵
1地域ごとに金150を消費し、
兵士収入を得る
ここで得ることのできる兵士ですが、
1地域ごとの兵士収入は
都市間の格差がありません
金や兵糧と異なり、
大都市の洛陽と極貧都市の新野でも、
「1地域の」兵士収入は等しくなります
(条件をすべて等しくすれば、一部の特殊地域を除く)
都市ごとの差が出るのは
「地域の数」と「都市・府・港関の割合」と「特殊地域」の3つです
1つ目:地域の数
地域の数が増えると、兵士収入は増えます
が、当然支出も増えます
なので、兵士の収入効率(兵士/金)は
都市によって変わることはありません
ただし、大都市の方が一気に兵士数を増やしやすいので
有利と言ったら有利です
代わりに、小都市(≒地域数の少ない都市)は
収入効率を上げやすいという優位点があります
募兵の費用は150×地域数であり、
任意の府だけから募兵することはできません
大都市では地域の数が多いため、
収入効率の低い(兵舎Lvや港)地域からも
募兵することが多くなります
一方、小都市は府の数が少ないので、
兵舎Lv上げや教化持ちを
全地域に敷き詰めやすいため、
収入効率を高めやすいです
ただし、これは漠然とプレイしているだけだと
中々活かすことが出来ません
2つ目:都市・府・港関の割合
地域にある拠点(都市・府・港関)によって収入が変化します
府のある地域の収入を1.0とすると、
港関は約0.7倍、都市は約1.3倍となります
そのため、港や関が多い都市は収入効率が悪くなります
また、地域数が少ない都市は、
都市1つに対して、府の数が少なくなるため、
若干収入効率が良くなります
3つ目:特殊地域
襄陽の宣城、陳留の梁など
一部の府では兵士収入が
都市と同様になっている地域が存在します
有名な地域が設定されていることが多いです
募兵は収入格差が大きくなる
先の通り、都市間での格差は、
(金・兵糧に比べると)少ないのです
その一方で、募兵に関する理解や行動によって
収入の格差は大きくなります
近似式のとおり、募兵での兵士収入は
倍率の高い重ね掛けが多いです
これを活かせるか否かにより、
収入の差が大きくなりやすいです
条件が整えば兵士収入が
府で750、都市で900を超えたりします
開発の効果が大きい
開発の兵舎は商業・農業と比べると
上げる価値が高いです
兵舎の開発は
1Lvにつき約27.5%ずつ収入が増えていき、
LvMAXでLv1の時の約2.1倍となります
これは商業・農業の伸びとあまり変わりません
しかし、前述の通り、
募兵では他の要素を倍々で掛けています
よって、開発で兵舎Lvを上げることで、
結果的に兵士収入を大きく増やすことが
出来るようになります
また、商業・農業に関わる金と兵糧は
探索・商人利用の方が効率よく稼げます
一方で、兵士収入は募兵以外だと、
限定的な手段(一騎捕縛、士気0などの負傷兵やイベント等)を
取るしかないため、
相対的に兵舎の価値が高くなります
加えて、兵舎Lvを上げると、
目標の兵数を確保するための費用も減ります
(支出の金150は動かないため)
すなわち、金銭面でも効果的ということです
以上の理由で、
メインの募兵場となる都市では
高Lvを目指す価値があると思います
開発でLv4や5にするのは大変ですが
とはいえ、金が足りないと募兵もできないので
最低限の金を貯めるまでは
商業もする必要があるかもしれません
関連
開発(商業・農業編)
召募の有無は大きい
募兵で大きなポイントは2点
まずは先述の通り、「兵舎Lv」を上げる事
そして、もう1つ大きな要素としては
全ての府に倍率でかかる「召募」の有無です
召募の個性を持つ武将を雇用するだけで
効果が得られるという即効性がありますし、
政策・戸籍整備のように、
他の政策とのトレードオフに
かけられることも無いので、
これの存在は非常に大きいです
また、ある程度の勢力になれば、
募兵を行う武将の武力差は少なくなってくるため、
この個性を持つ武将がいれば、それだけ有利となります
計算式の通り、武力とは掛かる場所が異なりますが、
武力換算をすると30以上の効果が確実にあります
(武力が上がると影響が大きくなる)
兵舎Lvの高いところに召募(+教化)持ちの武将を配置すれば
どんどん兵士を増やすことが出来ます
その他の要素
武力倍率
倍率自体は兵舎Lvと並んで大きいです
ただ先述の通り、ある程度の勢力になると、
高武力の募兵要員は確保しやすいです
そのため、勢力によって大きな差がつきにくいです
ただし、弱小で始める場合は
非常に影響が大きい要素になります
政策・戸籍整備
倍率が高いのですが、他に有用な政策もあるので
選択するかは状況次第でしょうか
部隊能力を上げることのできる政策を優先しがち…かもですね
Lv10の効果は強烈なので、
戦争をしていない時はつけてもいいかもしれません
とりあえずLv1をつけておけばコスパがいいです
人口・治安
隠し味程度の増加量になります
ただし、人口は5000になると
その地域では募兵そのものが
できなくなるので注意が必要です
教化
1地域にしか影響が無いため、
召募ほど重要では無いです
しかし、無視できるほど
効果が小さいわけでもないです
が、なんとなく配置してもそんなに活かせません
きちんと都市部や兵舎Lvの大きい地域に配置すると
効果を発揮してくれます
所持武将の数が多く、
文官タイプがよく持っている印象があります
拠点種類
都市は兵士収入が約1.30倍なので、
教化持ちがいるなら優先したいですね
都市規模を上げたいのなら、他の武将が優先ですが…
港や関は逆に収入が約0.7倍となるので、
兵舎Lvを上げたり、
教化持ちを配置する旨味は
少なくなります
募兵の担当について
小技みたいなコーナーです
募兵担当は月の下旬に都市に滞在していないと、
兵士収入が本来の50%となる
→裏を返せば、上旬中旬は探索などをしていてもいい
下旬に担当を変えると、その武将の能力が適用される
→上旬中旬は雑魚武将に担当させても収入は変わらない
ただし担当替えが面倒
→上旬中旬に担当無しは↓のケース
中旬、下旬から募兵を開始すると…
→費用は1月分きっちり取られる
その上で、
中旬開始は兵士収入2/3
下旬開始は兵士収入1/3
…下旬開始で募兵担当を探索などにだすと
戦いは数だよ兄者
とは言ったものの
実際の戦闘では部隊能力の方が重要だったり…
さて、意外と奥が深かった
募兵というコマンド
兵士数が増えれば
戦法の威力が上がったり
部隊の能力が上がったり
敵が都市から迎撃に出にくくなったり
敵勢力から狙われにくくなる
といった恩恵がありますね
兵舎の開発もリターンが大きいので
頑張ろうって気になれます
おわり
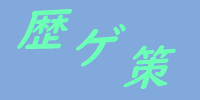 歴史ゲームの戦国策、ときどき他ゲー
歴史ゲームの戦国策、ときどき他ゲー